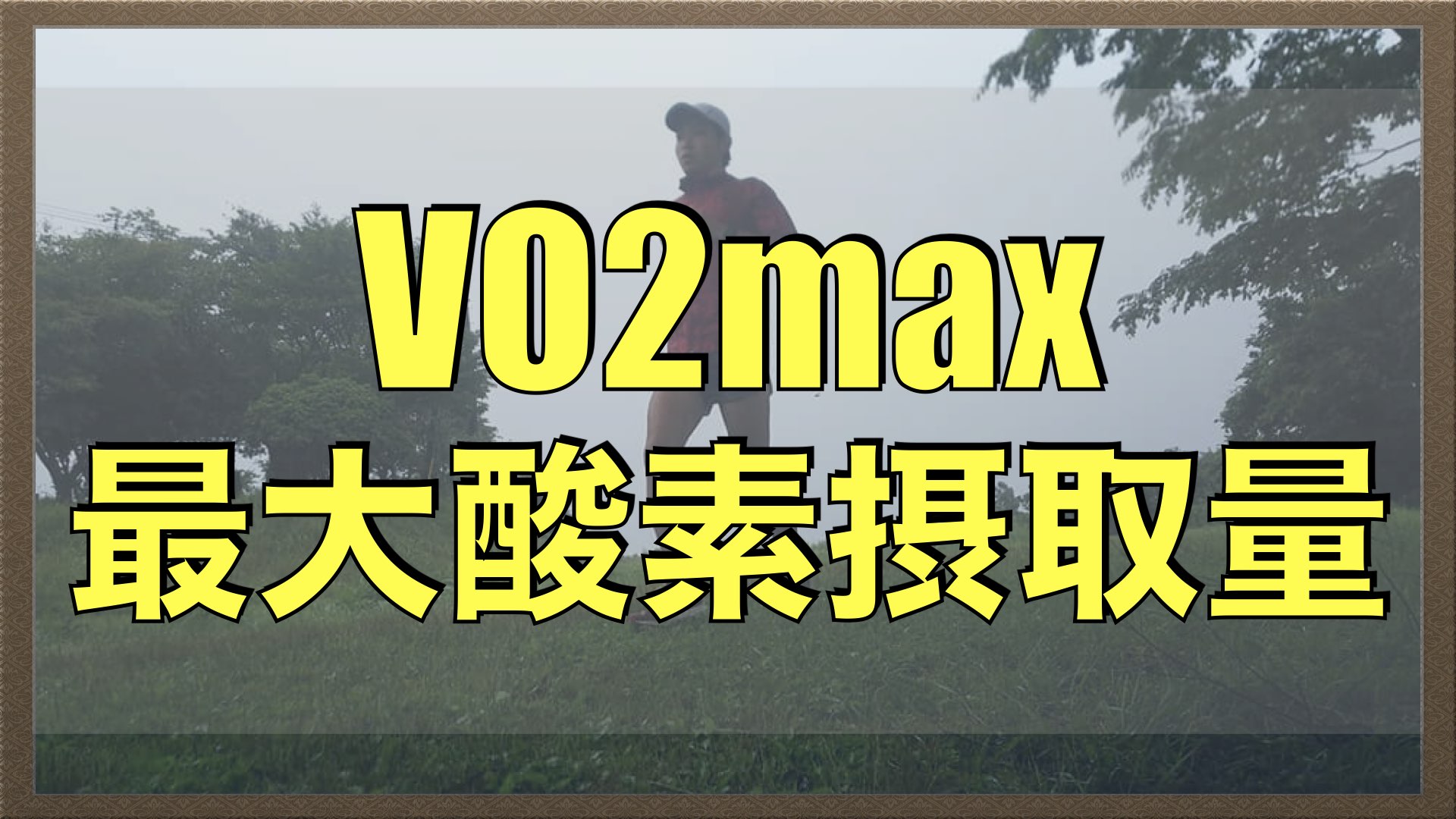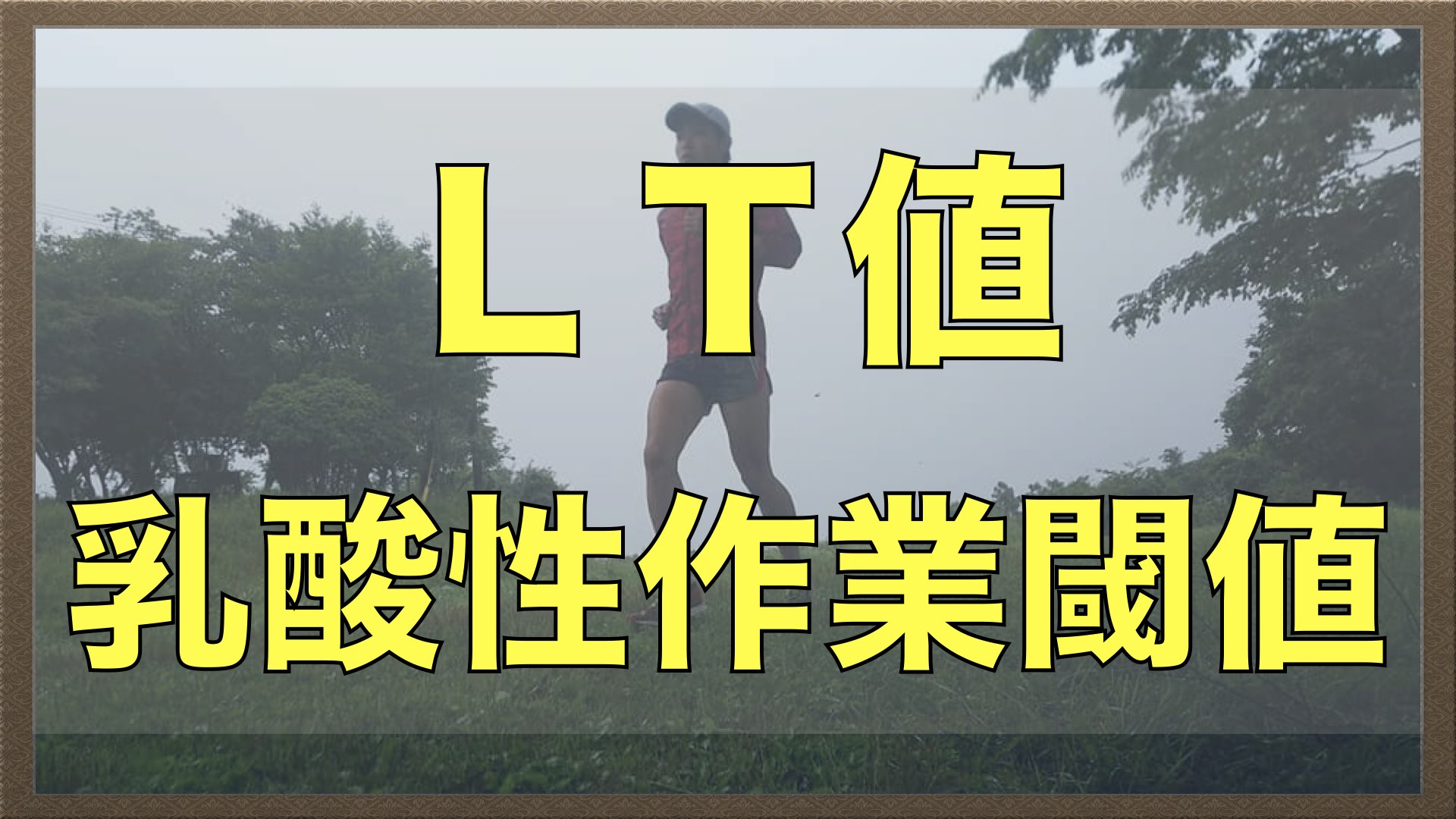マラソンの走力を決定する3大要素
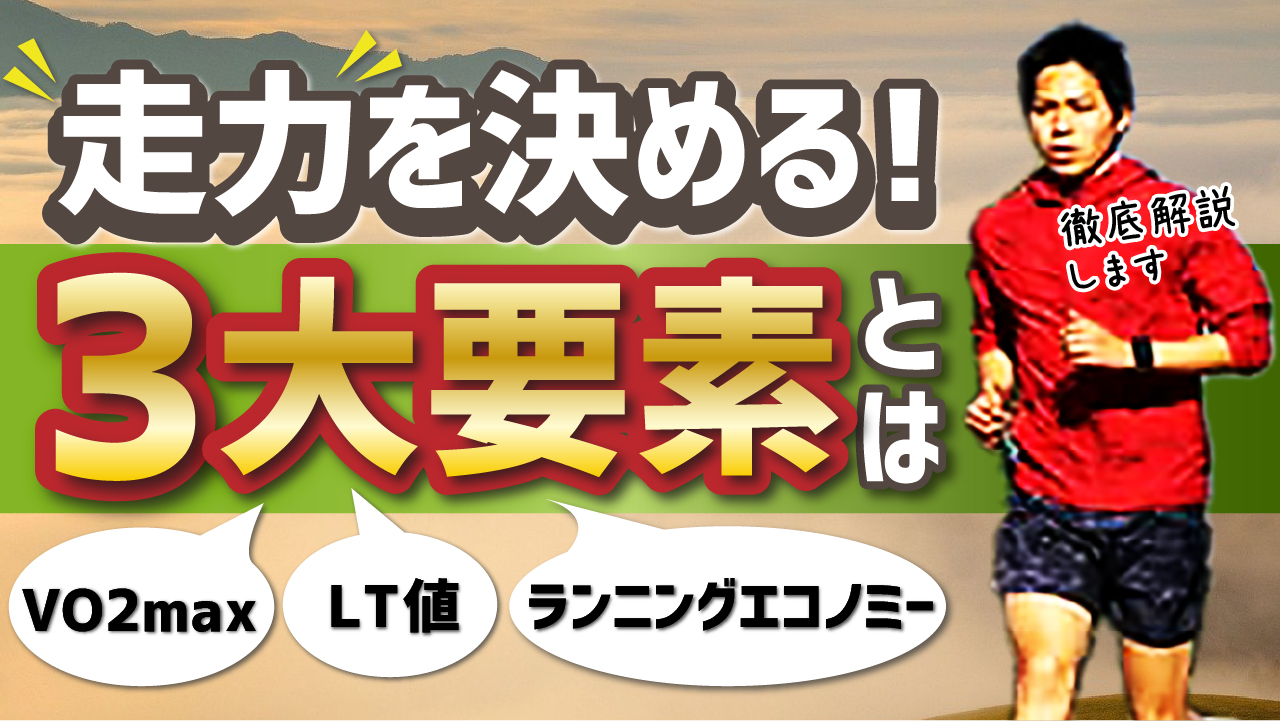
↓動画での解説はこちら↓
- マラソンの走力決定3大要素を理解し、マラソン練習の本質が分かる。
- マラソンの記録を伸ばす為に、自分のどういう能力を鍛えるべきかが分かる。
マラソンの走力決定要素【3つ】
まずいきなりですが、結論から言います。
「マラソンの走力を決定する要素は大きく3つある!」
マラソン初心者もマラソン経験者も、これだけは押さえておきましょう。 マラソンの走力を決定する3大要素は以下の通りです。
- VO2max (最大酸素摂取量)
- LT値 (乳酸性作業閾値)
- ランニングエコノミー (経済性)
以上の3つの能力を高めればマラソンの記録は確実に伸びます。
「自分のどういう能力を鍛えるべきか」を知ろう
世の中にはいろんなマラソントレーニングが紹介されていますが、あなたはそれらの練習の意味を理解していますか?それらの練習をすることで「マラソン走力決定3大要素」はちゃんと鍛えられていますか?
もしその答えがNOならば、その練習はあなたのマラソンの記録を向上させる練習としては効果が 薄いです。なぜなら、目的がない、あるいは目的に正しく向かっていないからです。
「今取り組んでいるこの練習は、自分のどういう能力を鍛えているのだろうか?」 ということを常に意識しましょう。
「ダニエルズ理論」のダニエルズ氏の言葉を借りると、
常に必要なのは、「この練習の目的は何か」という問いに答えられることだ。
『ダニエルズのランニング・フォーミュラ』 / ジャック・ダニエルズ 著 より
ということです。
それでは、
- VO2max (最大酸素摂取量)
- LT値 (乳酸性作業閾値)
- ランニングエコノミー (経済性)
それぞれの概要をサクッと紹介していきます。
VO2max (最大酸素摂取量)
一定時間内に酸素を体内に取り込める最大量
※ よく使われる単位 : ◯◯ ml / kg / min
(1分間に体重1kgあたり◯◯mlの酸素を取り込む事ができる)
マラソンのような有酸素運動においてはどれだけ多くの酸素を取り込んで運動エネルギーに変え られるかという能力が非常に重要です。この「VO2max (最大酸素摂取量)」が高いランナーは “(有酸素的な)最大スピード”が高いと言えます。
また、「VO2max (最大酸素摂取量)」は3~5分間走の繰り返し(ペースはI(インターバル)ペース)で鍛えられると言われています。
その為、「VO2max (最大酸素摂取量)」を鍛える代表的な練習としては・・・
1000m × 5本 インターバル
P(ペース) : I(インターバル)ペース = VO2maxペース
R(リカバリー) : 200m = 90~120秒 ジョグ
※ インターバル : 速いランニングと短い休憩(リカバリー)を繰り返すトレーニングのこと
などがあります。
LT値 (乳酸性作業閾値)
「血中の乳酸濃度が急激に上昇するポイント」
※ LT : Lactate Threshold
この「LT値 (乳酸性作業閾値)」を超えると、体内には乳酸が急激に溜まって、呼吸が苦しく、身体が動かなくなり始めます。
つまり「LT値 (乳酸性作業閾値)」とはラクに走れるペースとキツくなり始めるペースとの境界のようなものです。したがって、「LT値 (乳酸性作業閾値)」を向上させることによって“ラクに走れる最速ペース”が引き上げられます。
LT値を超えたペースで走っていると身体は疲労に耐えられなくなり、マラソンではペースダウンしてしまいます。そう言う意味では、LT値は“持久力”を表すとも言えます。
また、
LT値 (乳酸性作業閾値) :
20~30分間程度継続できる運動強度(ランニングペース)
と言われており、このランニングペースを「ダニエルズ理論」ではT(閾値)ペースと言います。
このT(閾値)ペースで走る総距離を増やしていくことで「LT値 (乳酸性作業閾値)」の向上が期待できます。
具体的な練習メニュー例としては・・・
2km × 3~5本 クルーズインターバル
P(ペース) : T(閾値)ペース
R(リカバリー) : 3~5分 ジョグ
※ クルーズインターバル : 速いランニング(≒LTペース)と短い休憩(リカバリー)を繰り返すトレーニングのこと
などがあります。
ランニングエコノミー (ランニングの経済性)
「少ないエネルギーでいかに速く長く走れるか」という効率性のこと。
「ランニングエコノミー (経済性)」は様々な要素から構成されています。
それらの要素は複雑に絡み合っているのですが、なるべく体系的に表すと以下のようにまとめることができます。
- 「エネルギー代謝」的要素
- 「筋肉・循環器」的要素
- 「フォーム」的要素
■ 参考 : ランニングエコノミーの考え方 (アスリートLab)
僕が調べた限り、日本語で最も分かりやすく体系的にまとめてくださっていたのが、アスリートLabさんの記事だったので参考にさせていただきました。
「ランニングエコノミー (経済性)」は様々な要素が関わり合っている為、分かりやすい指標はあ まりないのですが、概念としては非常に重要です。
「ランニングエコノミー (経済性)」を向上させる方法としては例えば・・・
[エネルギー代謝]
- エネルギー効率の良い脂質代謝を促す為に、空腹時に走る
- 糖質代謝の節約する為に、“閾値トレーニング”を行う。
[筋肉・循環器]
- 速筋(速く走るため)と遅筋(長く走るため)をバランス良く使う。
- LSDを行い、全身の毛細血管の発達を促す。
[フォーム]
- エネルギーロスの少ないランニングフォームを身につける。
などがあります。
マラソンの記録が停滞している人こそ
“基本に立ち返るべき”
最後に、もう一回だけ「マラソン走力決定3大要素」の重要性を。
- 今まで単純に走ってきただけだったけど、最近伸び悩んでいるなぁ。
- そろそろ憧れの「サブ3」を狙いたい。
- でも、最近記録が頭打ちで停滞気味・・・
- 何か突破口を見出したい。
以上の方々のように、マラソンの記録が停滞している人こそ“基本に立ち返る”ことが重要です。
巷では、様々なトレーニング情報が飛び交っており、それらの中には有益なものもありますが、 真偽が定かではない眉唾(まゆつば)物の情報も多々あります。
情報が溢れる中で混乱する方もいらっしゃるかもしれませんが、マラソン練習の“原理原則”的なものは限られています。こういった“原理原則”は迷った時に立ち返るべき基本なので、常に心に留めておきましょう。
そして、今回紹介した「マラソン走力決定3大要素」も“原理原則”的なものと言って良いでしょう。
繰り返しますが、
- VO2max (最大酸素摂取量)
- LT値 (乳酸性作業閾値)
- ランニングエコノミー (経済性)
以上の3つでマラソンの走力は構成されており、この3つをそれぞれ伸ばしていくことでマラソン の記録は向上するのです。
これが基本のキ。マラソン練習の本質部分です。
◆ まとめ ◆
『マラソンの走力決定3大要素』
① マラソンの走力を決定する3大要素は・・・
- VO2max (最大酸素摂取量)
- LT値 (乳酸性作業閾値)
- ランニングエコノミー (経済性)
② ①の3つの能力をそれぞれ鍛えることでマラソンの記録は向上する。(マラソン練習の本質)
③ 今取り組んでいる練習は「マラソンの走力決定3大要素」のいずれかをちゃんと鍛えることができているか、常に確認しよう。